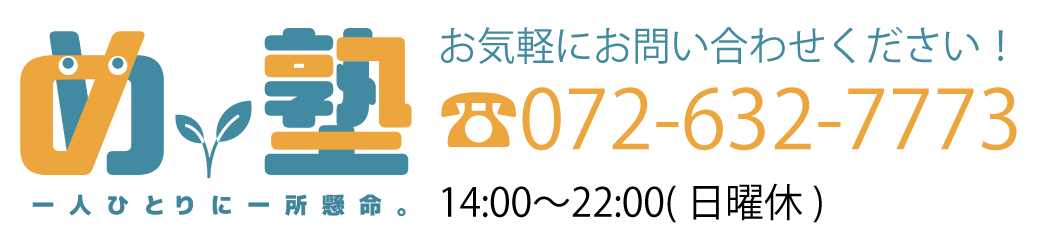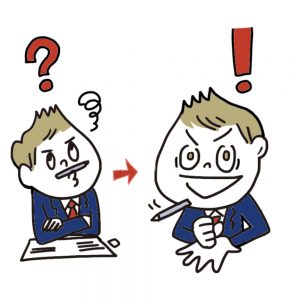中3の理科の勉強
現在め塾では夏期講習中です。
今日から中3の理科のタームが始まります。
中学生の理科の勉強は
「考えなければいけない部分」と
「覚えなくてはいけない部分」とを線引きして勉強するととてもよく伸びます。
あと、イメージすることです。特に数学と理科はイメージすると解ける問題がとても多いです。
ただ、中学生にはその線引きが難しいとは思います。
時々「理科なんて覚えたらいいだけじゃないんですか?」という方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
全部全部覚えていたら頭がパンクします。
でも、茨木高校に行くような生徒の場合、全部暗記して高校入試にのぞむ生徒もいます。しかもそれで合格もします。
でも、高校になってから(特に茨木高校のような進学校では)その勉強法では通用しません。
いくら茨木高校のような進学校に入学できても、そこがゴールではなく、大学入試まで考えなくてはいけないのに・・・
と思います。
理科の勉強の話に戻します。
ほとんどの中学生が「密度=質量÷体積」などと公式を覚えます。(本当は分数で習うのですが、ここには分数は書きにくいので、割り算で書いています。)
この公式を覚えても
「同じ質量でも体積が大きいのは、密度の大きいAか密度の小さいBかどちらでしょう?」
という問題は解けない生徒も多いです。
正解の確率は2分の1なので、AかBか適当に答えても2人に1人は正解です。
なのでこの1問が正解していたからといって、理解していると考えるのは早計です。
密度の大きい鉄と、密度の小さい発泡スチロールをイメージしてください。
鉄を10g持ってくると、どれくらいの大きさになる?
そう、手のひらに鉄釘10本分くらいやね。
発泡スチロールを10g持ってくると、どのくらいの大きさになる?
大きさはよくわからんけど釘よりかは体積が大きいよね?
鉄は密度が大きくて、発泡スチロールは密度が小さいんよね?
じゃ、さっきの問題で、密度の大きいAか密度の小さいBかどっち?
とイメージして考えるとみんな正解を答えます。
でも、生徒はこういうイメージをすることが面倒くさいんです。

しかし、同じような問題を何問か解いているとイメージすることが面倒でなくなってきます。
こういう練習をすれば理科がムチャクチャ得意になっていくのですが、考え方がわからないんです。解答の解説を見たり公式から解こうとしたりして間違えます。
イメージしさえすれば、小学生でも解けるのに。
め塾ではイメージして解かせることを教えています。
こういう考え方は高校生になっても通用しますよ。
きちんと理科を勉強させたかったらぜひめ塾へ!
(なんや、宣伝かい!)