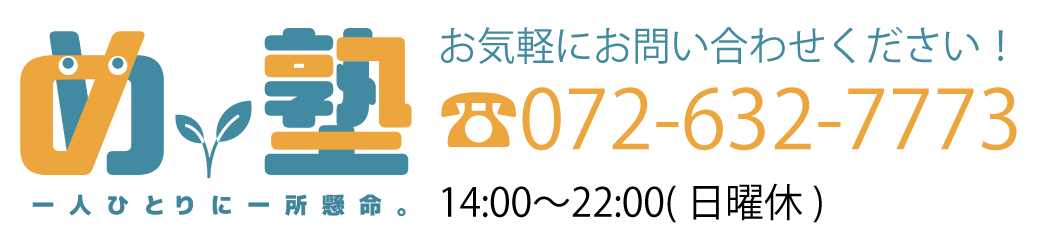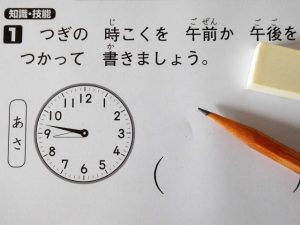文章問題で何を聞かれているのか?
理科の計算問題が高校合格の合否を分けるという内容のブログを前回書きました。
大ざっぱに説明しますと・・・
知識問題は解けて当たり前、解けない人が高校落ちます。
計算問題を解ける生徒が合格します。
というような内容でした。
で、め塾の夏期講習では1年生は密度の計算問題の特訓をしてできるようにしました。
結構、難しい問題でもスラスラと解いてくれるようになりました。
みんなができていないポイント
を書いていきたいと思います。
塾に来ていない人は、この部分を徹底的に鍛えれば塾もいらないかもしれません。
1、基本的に文章問題を読んで、何を聞かれているのかが理解できる
ここを間違われると、いくら理科の知識があっても正解しません。
例えば
「Aくんが茨木市から15km離れている高槻市まで30分間で走りました。
Aくんが1時間あたりに走った距離は何kmでしょう?」
実際にお子さんに聞いてみてもらってもいいかもしれません。
「この問題で何を聞かれていると思う?」
とお子さんに聞いてみてください。
結構な確率で間違えると思います。

1、「距離」と答えた子
残念、バツです。
確かに文章としては距離を聞いているように見えます。
でも、問題を作った人が一番引っかかってほしい答えです。
実際に「距離」を聞かれると「速さ」×「時間」で計算すると思います。
「時間」は問題文中に書いてありますが、「速さ」は書いてないです。
2、「Aくんが1時間あたりに走った距離は何kmでしょう」と答えた子
残念、バツです。
小学生の時の国語でこういうふうに答えなさい、と教わったのかもしれません。
とにかく書いてある通りに言います。
3、「速さ」と答えた子
正解です!!
1時間あたりに進む距離のことを「速さ」と言います。
この問題では、速さの定義のようなものが問われています。
こういう本質を理解しているかどうか?というような問題がこれから問われるようになっていきます。
今までのような「丸暗記」で乗り切れるような受験問題はどんどん減っていくでしょう。
仮に、「丸暗記」で受験が乗り切れたからといって、それでいいでしょうか?
ちゃんと理解すれば「わかる楽しさ」もあると思います。
ある程度まできっちり勉強すれば、勉強は辛いものではありません。面白いものです。
勉強を面白くしませんか?